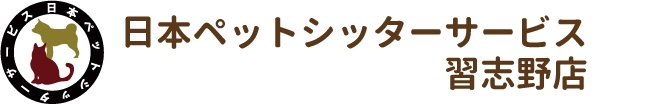獣医師のいるペットシッター「わんちゃんのデンタルケア編」その①
こんにちは!獣医師の柏木です。
前回はお口の中のお話をしました。
今回はワンちゃんのデンタルケアについてお話しします。
?デンタルケアグッズってどんなものがある?
✅歯ブラシ
✅歯磨きジェル
✅ガーゼ
✅歯磨きガム
✅水に溶かして使うもの
✅ロープなどのおもちゃ
しっかり歯の汚れを落とすという意味では歯ブラシが1番有効です。
 歯ブラシの始め方
歯ブラシの始め方
今まで歯ブラシを使ったことがない子に、急に歯ブラシをすると嫌な印象を与えてしまい、その後も歯ブラシをするのがとても大変になってしまいます。なので徐々に歯ブラシに慣れさせることが重要です。
以下の手順でお口周りのケアを慣れさせましょう。
まずは手で
①口まわりを触る
②上唇、下唇を触る
③前歯、その周りの歯茎を触る
④奥歯、その周りの歯茎を触る
ここまで触れてから次に歯ブラシにステップアップです
⑤歯ブラシを前歯、歯茎に当てる
⑥歯ブラシを奥歯、歯茎に当てる
🌟歯ブラシにわんちゃん用の美味しい味のする歯磨きジェルを着けて行うといいですよ!🌟
⑦歯を磨くことにチャレンジ!🏁
上記の工程は1日で行うのではなく、1週間以上かけて徐々にステップアップしてくださいね。
1つできたら必ずご褒美をあげたりたくさん褒めてあげてください!
ゆっくりステップアップしてご褒美をあげることによって、歯磨きが怖いことではなく楽しいことに変わっていきます。ワンちゃんとコミュニケーションをとりながら楽しく行いましょう!
歯ブラシがうまくいかない場合は、手にガーゼを巻いて同じ工程でおこなってください。ガーゼの方が、手の感覚に近いので怖がりにくいです。
⚠️注意点⚠️
🦷無理せずにゆっくりステップアップしましょう。
🦷1番歯石がつきやすいのは”奥歯”です。”奥の1番大きい歯”が見えるまでしっかり歯茎をめくって確認してください。
🦷ワンちゃんの歯はデコボコしています。横向きだけでなく、縦や斜めにも磨いて磨き残しがないようにしましょう。
🦷歯茎からすぐに血が出たり、とても痛がるようなら歯周病の可能性があります。病院へ相談しましょう。
次回はその他のデンタルケアグッズについてお話しします。
獣医師のいるペットシッター「病気のサインかも?④ 口の中の違和感」編
こんにちは!獣医師の柏木です。
今回はお口の中のお話です。
おうちのワンちゃんやネコちゃんの口臭や鼻炎、硬いものを食べなくなった等の症状、気になりませんか?
ワンちゃん、ネコちゃんは虫歯にはならないと言われていますが、歯肉炎や歯周病になります。
歯肉炎は進行すると口の中の異臭だけでなく、頬の腫れ、鼻炎、口の痛み、さらに口の中の菌により、心臓や肺など他の臓器などのさまざまな病気の原因になります。
📝口に違和感がある時のサイン📝
✅よだれや、よだれによる口周りの汚れ
✅くしゃみや鼻水
✅異臭
✅食べる量の低下
✅前足で口周りを擦る
など…
歯肉炎の主な原因となるのは、歯垢からできる歯石です。
歯垢はごはんの食べカスから成り、そのまま放置してしまうと、2, 3日で歯石へと変わります。
一度歯石になってしまうと、専用の器具での処置をしないと中々取ることができません。
そのため人と同じように歯ブラシなどを使い、歯垢を落とす毎日の🪥デンタルケア🪥が重要です。
しかし、歯肉炎へと進行した歯の場合、歯茎の炎症により歯磨きを痛がる傾向にあります。
その場合、まずは病院で歯石取りをして歯石をしっかり落とし、歯肉炎を治してからケアをしてあげましょう。
また、歯肉炎だと思っていたら他の病気(口腔内腫瘍など)の場合もあります。
気になることが有れば相談してくださいね。
次回はワンちゃんの歯磨きの仕方についてお話しします。
獣医のいるペットシッター「ワンちゃんのトイレ」編
こんにちは!獣医師の柏木です。
今回はワンちゃんのトイレ環境のお話をします。
粗相などトイレトレーニングがうまくいかない、トイレの悩みがある方はぜひ試してみてください。
まず、ワンちゃんの好むトイレ環境はペットショップやブリーダー宅でのトイレ環境に順ずることが多いです。
それは、ワンちゃんは🐾足の裏の感触🐾でトイレを覚えるからです。そのため幼少期で過ごした場所でのトイレ環境に慣れていることが多いのです。
<例🚽>
網付きトイレ
新聞紙
ペットシーツなどなど

トイレトレーニングがうまくいかない場合は、トイレの種類を変えてみましょう。
また、お外でしかしない子もいますね。お外にすぐ行ける環境であれば問題ありませんが、お留守番が長かったりすると膀胱炎などの下部尿路疾患のリスクが上がってしまいます。
その場合、散歩中のトイレをしそうなそわそわしたタイミグですぐにペットシーツの上に乗せて、足の裏がペットシーツの感触に慣れると室内でもしてくれる様になります。
しっかりトイレでできた時はたくさんほめてあげてくださいね。
⚠️ご褒美でオヤツをあげる時⚠️
ご褒美でオヤツを使うのもとても有効です。トイレしたら良いことがある✨と結びつけ易いように、うまくいったらすぐにご褒美をあげましょう。
しかし、オヤツをもらうのが嬉しくてわざと尿を小出しに何回もトイレに行くことがあります。オヤツを使ったトイレトレーニングの際は徐々にオヤツの頻度を減らしてあげるといいでしょう。(例 トイレができたら毎回ご褒美→2回に1回→3回に1回→外出時など特別な時のみ)
さらに、トイレを囲うものによる閉塞感を嫌がる子もいます。
その場合は囲うものを少し低めに変えてあげましょう。
また、トイレ周りに便や尿が出てしまう子は足だけ乗っていてお尻は出ていることがあります。大きさを広めにとってあげるだけで解決したりすることも!
どうでしょうか?
おトイレ問題を抱えている方はぜひ試してみてください。
あまりにも粗相が多い場合、実は病気が隠れていたりすることもあるので、病院を受診してくださいね。
(詳しくは以前投稿した「病気のサインかも?」③ おしっこの回数 をご覧ください)
獣医師のいるペットシッター「病気のサインかも?」③ おしっこの回数
こんにちは!獣医師の柏木です。
今回は、わんちゃん猫ちゃんのおしっこの回数についてです。

まずは1日の正常な回数ですが、
わんちゃんは3〜5回
猫ちゃんは1〜3回
と言われています。しかし、年齢やその子によって変わってきます。日頃からチェックして1日のだいたいの回数を把握し、すぐに変化が分かるようにしてあげましょう!
①トイレに行く回数が増えている。
•1回の尿量は普通または多め
飲水量の増加から尿量の増加によるもの。多飲多尿の症状が疑われます。(詳しくは前回の多飲多尿の記事へ)
•1回の尿量は少なめ
膀胱に尿がためられない状態。膀胱炎やストレスが疑われます。(※わんちゃんの場合、おやつを使ったトイレトレーニングによって少量ずつ出す子もいます。こちらの場合は健康です。)
•⚠️尿が出ていないのにトイレに行く(排尿姿勢をとる)⚠️
こちらは何らかの原因(主に尿道の腫れや尿結石の詰まり)で尿が外に出てかない状態が疑われます。放置してしまうと腎臓に負担がかかりかなり危険な状態です!
すぐに病院に連れて行き、排尿の処置をしてもらってください。
②トイレに行く回数が減っている。(トイレではない場所での排尿を除く)
•⚠️1回の尿量は少なめ⚠️
尿が作られていない状態。末期の腎臓の病気や重度の脱水が疑われます。すぐに病院へ‼
•1回の尿量が多め
トイレに行くのを我慢する原因があるかもしれません。トイレ環境を見直してみましょう。放っておくと膀胱炎などの原因になります。
また特に猫ちゃんの場合、環境の変化(引越し、お留守番、お客さんが来たなど)によって1日我慢してしまう子も多くいます。目安としては丸1日以上出てない場合は受診をおすすめします。
まずはぜひその子の普段のトイレへ行く回数を把握してください。そして些細な変化も見逃さないようにして早期発見できるようにしましょう。何か気になる点があればご相談くださいね。
次回は適切なトイレ環境についてお話しします。
猫ちゃんにお水を飲んでもらうには(前編)
こんにちは!獣医師の柏木です。
前回わんちゃん猫ちゃんの多飲多尿のお話をしましたが、猫ちゃんにとってお水を飲むということは健康に繋がる大切なことです。
今回は猫ちゃんの飲水量をアップする方法のお話をします。
猫ちゃんは10歳を超えると半数以上の子が腎臓の病気を罹ってしまいます。猫ちゃんは元々お水をたくさん飲む生き物ではないため、腎臓に負担がかかりやすいのです。
諸説有りますが、猫ちゃんは元々砂漠で生活する生き物だったため、お水を飲む習慣が少なかったからと言われています。
腎臓は尿を作る臓器のため、身体が脱水状態だと大きな負担がかかります。そこで腎臓病のリスクを下げるために、お水をたくさん飲むことがとても大事です。
また、すでに腎臓病の子にとってもお水を飲むことが進行を遅らせることに繋がるので、飲水量が気になる方は試してみてくださいね。
まずチェックして欲しいこと📃
✅器の種類
✅器の数
猫ちゃんは、水を飲むときにヒゲが器などに当たると不快感を感じます。
なので水を飲む時にヒゲが当たらない大きな器でお水をたっぷり入れて顔を突っ込まなくても飲める状態が良いでしょう。
敏感な子は器の臭いも気にします。
プラスチックや金物よりも、陶器の器が好ましいです。
猫ちゃんによっては飲む場所に好みもあります。

うるさい所やトイレの近く、寒すぎたり暑すぎたりする所は好みません。
そして飲みたい時にすぐ飲めると良いので、各部屋に1個以上置くのがベストです。
まず、以上の点を注意してみてください。
 ただしコップから飲むのが好きな子やお風呂場の溜まったお水を飲むのが好きな子もいます。色々な器や場所を試して飲む量をみてその子に合わせてくださいね。
ただしコップから飲むのが好きな子やお風呂場の溜まったお水を飲むのが好きな子もいます。色々な器や場所を試して飲む量をみてその子に合わせてくださいね。
次回はさらに細かく飲水量をアップさせる方法をお話しします。
それって病気のサインかも? 多飲多尿編
こんにちは!獣医師の柏木です。
今回は病気のサインの可能性がある”多飲多尿”の症状のお話です。
うちの子は大丈夫か?チェックしてみてくださいね。

そもそも多飲多尿とは…
<通常より尿の量が多くなることによって、飲水量が増えている状態>
1日の飲水量の 目安として、
ワンちゃん🐶では”体重Kg✖️100ml以上(4kgの子で400ml以上)”
猫ちゃん🐱では”体重kg✖️70ml以上(4kgの子で280ml以上)”
です。
もしこの量を超えている場合に考えられることは
☑️腎臓病(特に猫ちゃんに注意)
☑️腫瘍
☑️子宮蓄膿症(避妊手術のしていない女の子)
☑️糖尿病
☑️尿崩症(かなり稀)
☑️その他ホルモンの病気
☑️心因性(環境の変化やストレス)
☑️気温(夏など暑い季節や乾燥している時)
があります。
上記の病気は病院の血液検査等で確認ができます。
気になる場合は早めに検査してもらいましょう。
⚠️注意していただきたいのは⚠️
飲水量を減らせば治る病気ではありません。
無理やり減らすと悪化します。
お水は飲みたいだけ飲ませてあげてください。
📃チェックの仕方
- お皿に入れる前に何ml入れたかを把握して、入れ替えるタイミングでどれくらい残っているか確認する。(蒸発の関係で数mlの誤差があります)
- 500mlのペットボトル(大きい子は1L)を用意して随時そこから足すようにして、ペットボトルに残った量で大体の量を確認する。5kg以下の子は500mlまるまる飲んだ時点で多いと判断できるので、分かりやすいです。その子の体重に合わせて線を引いたペットボトルがあると楽ですね。
毎日やらなくても月に1〜2回でいいので確認してみましょう。
飲水量が多かった場合、2~3日続けて測ってください。続かない、かつ、元気であれば問題ありません。
⚠️尿量が増えたことで発覚することも多いです⚠️
ワンちゃんではペットシーツを変える回数が普段より増えていないか?
猫ちゃんではオシッコの玉がいつもより多くないか?
見てみてください。
早い発見、治療がわんちゃん猫ちゃんの健康に繋がります。
この場合はどう?等気になることがあればご相談ください。
獣医師のいるペットシッター「猫ちゃんのシャンプー」編
こんにちは。
当店スタッフ、獣医師の柏木です!
今回は猫ちゃんのシャンプーについてのお話です。
基本的には猫ちゃんはワンちゃんとは異なり、シャンプーは必要ありません。

猫ちゃんは水やドライヤーが苦手なので大きなストレスがかかります。不十分なドライヤーによって毛玉になることも有ります。
猫ちゃんはとても綺麗好き。自分でグルーミングをしますのでシャンプーをしなくても基本的に皮膚は良好に保たれます。
!長毛種さんはブラシが必要!
長毛種さんは自分でのグルーミングが追いつかずに毛玉になってしまうことが多く有ります。
毛玉になる前にブラシをしてあげて予防しましょう。
長時間ブラシをするのを嫌がる子は、今日は右側、明日は左側、次にお腹…と小分けにするのもおすすめです。
ひどい毛玉を自己処理しようとすると皮膚にダメージが起こりますので、その場合はかかりつけ医に相談しましょう。
!シャンプーをする場合の注意点!
皮膚の病気や外の子をお迎えした場合はシャンプーが必要になることが有ります。
シャンプーする場合は<洗濯ネット>の使用がおすすめです。
なるべく短時間で終わらせましょう。
また、ワンちゃんには使えても猫ちゃんには使えないシャンプーも有るので、必ず「犬用」「猫用」の表記を確認してください。
ワンちゃんのシャンプー
こんにちは。当店スタッフ、獣医師の柏木です!
今日はワンちゃんの皮膚とシャンプーのことをお話しします。
よくシャンプーをする頻度はどれくらいがいいのか?という質問をいただきます。
ワンちゃんの皮膚のターンオーバー(肌の細胞の入れ替わる期間)は人の皮膚と同じ2週間程度。
これは長毛種、短毛種も同じです。
この期間を目安にシャンプーをして皮膚を清潔に保つことが皮膚の健康へと繋がります。
過剰すぎたり、怠っていると皮膚炎につながってしまいます。
また、シャンプーする場合は人の皮膚とpHが異なるためワンちゃん用のシャンプーを使用してくださいね。
足の裏など汗をかきやすいところは菌が増えやすいので、1日1回のシャンプーは効果的です。
!皮膚炎が起こっている場合は異なります!
皮膚炎が起こってしまった場合にも、シャンプーは治療の一貫としてとても重要な役割になります。
しかし、間違ったシャンプーの選択や使用方法によって皮膚のバリアが弱くなり、逆に症状の悪化が見られることもあります。
皮膚の状況に合わせて最適なシャンプーの種類や頻度が変わりますので、気になることがあればご相談ください。
まだまだ熱中症対策
こんにちは。
当店スタッフ、獣医師の柏木です。
今夏はいつまでも本当に暑いですね…人だけでなく、わんちゃん猫ちゃんにとってもまだまだ注意が必要な季節です。
今回はお留守番中にも取り入れて欲しい熱中症対策のお話です。
①温度湿度の対策を
わんちゃん、猫ちゃんにとっての快適な温度は26℃前後です。
見落としがちなのが湿度。温度の調節はしっかりやっていたのに熱中症になってしまった…という子が時々います。
その場合は湿度を見逃してしまっていることがあります。50-60%を目安に調節しましょう。
また、冷風が直接身体に当たると体がダルくなってしまうことが。直接当たらないように風向きには気をつけてください。
そして部屋の温度が寒すぎた時や、停電などでクーラーが停まってしまった場合に場所の移動ができるよう、涼しく環境を整えた場所以外にも廊下や玄関など自由に行き来できるようにしておくといいでしょう。
②お留守番時には万が一に備えて
出かける前には飲み水は必ず新鮮なものに変えましょう。
器は1つだけでなく、こぼれた場合や飲み干した場合を考えて必ず複数置いてください。
!停電時に備えて!
自動給餌器や給水機は停電時に停まってしまいます。電気を使わないタイプのものも用意しましょう。
前述にもお話しましたがクーラーが切れてしまう場合もあります。
2Lのペットボトルのお水を冷凍庫で凍らせた氷柱を部屋の中に置いておくと万が一の時も、氷柱の冷気で涼めます。
また、日中でも室内のカーテンを引いて室温の上昇を防ぎましょう。特に陽当たりのいいお部屋には遮光、断熱のカーテンをひくといいでしょう。
猛暑続きの暑い夏ですが、人も動物も元気に乗り越えていけるよう注意していきましょう!
また、この場合はどうなのだろう?等気になることがあればお気軽にご相談下さいね。
![]() 歯ブラシの始め方
歯ブラシの始め方![]()
![]()